水産部門の再生が商機を生む(3/6)
スーパーマーケット経営支援セミナー第一弾
水産部門の再生が商機を生む
3.本当に、魚離れが進んでいるのか?
まずは、下記のグラフを見てみましょう。
魚介類購入先の変化
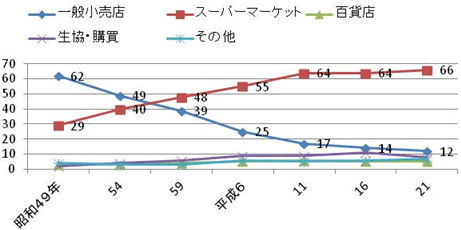
資料:総務省「全国消費実態調査」
一般的に家庭の主婦が水産物・鮮魚などを購入するところは、食品スーパーが6割とも7割とも言われています。
いっぽうで「魚離れ」と言われながら、回転寿司チェーン・業界や持帰り寿司、一部の魚専門店では、お客様からの高い支持・人気を得て、業績を伸ばしています。
回転寿司業界の市場規模推移
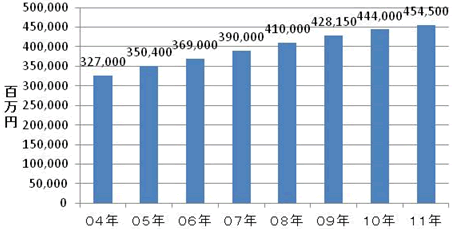
資料:日本コンサルタントグループ調べ
次に、魚種の購入数量を見てみましょう。
購入数量が増加した魚種、減少した魚種
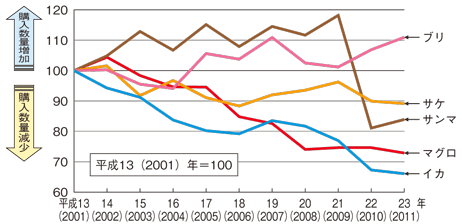
資料:総務省「家計調査」
(二人以上の世帯(農林漁家の世帯を除く))に基づき水産庁で作成
多魚種が購入数量を減少傾向にある中「ぶり」は逆に増加しています。「ぶりしゃぶ」や「炙り・たたき」などの食方の普及による影響とも言われています。
次に、世界の供給量はどう変化しているか見てみましょう。
世界の食用魚介類の国別供給量の推移
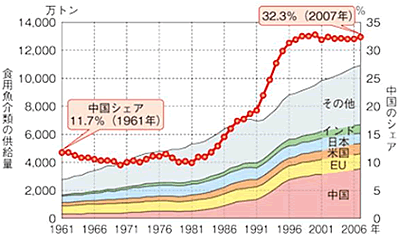
資料:FAO「Food balance sheets」及び農林水産省「食糧需給表」
世界的には「魚食」が大きなブームとなり、日本の順位が落ちていると言われています。
食品スーパー水産(鮮魚)部門として、地域のお客さまを理解し、お客さまのために、新たな売るための仕掛けは行なわれていますでしょうか?
目次:
- はじめに
- 低迷する水産(鮮魚)部門の現状
- 本当に、魚離れが進んでいるのか
- 低迷する水産(鮮魚)部門の再構築
- 水産部門政策と商品部に求められる力
- 「水産部門の再生が商機を生む」のご案内
